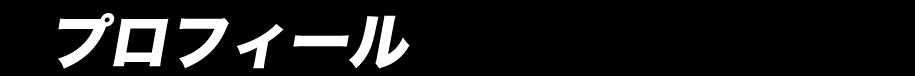
チーフトレーナー
早川 友登
(はやかわ ゆうと)

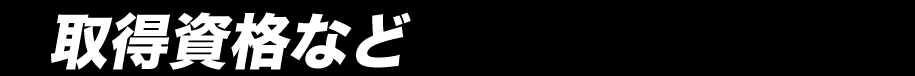
NSCA(全米ストレングス&コンディショニング協会)認定資格取得
ViPR(バイパー)認定インストラクター
日本トレーニング指導者協会認定トレーナー(JATI-ATI)
清水国際高校アメリカンフットボール部 元ヘッドコーチ

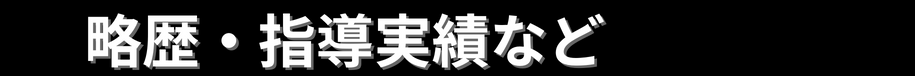
清水国際高校
関東学院大学
東京スポーツレクリエーション専門学校
トレーニングスタジオ13チーフトレーナー
2014〜2017 清水国際高校アメフト部ヘッドコーチ
2018〜2021 清水国際高校卓球部ストレングスコーチ
2020.4~ オンライントレーニングを開始
2022.3 SBSテレビ「#オレンジ」出演

中高生のポテンシャルアップ、介護予防
身体のケアに関する講演を行っております。
2025年6月現在
指導人数は、年齢10代から90代まで約200人。
(運動選手は110人)
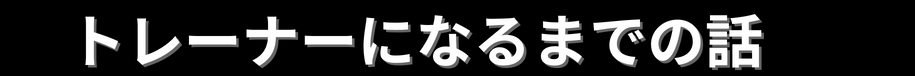
はじめて本格的にはじめたスポーツは中学時代のソフトテニスでした。
高校からアメフト部に入部。
入部した動機は、
「アメフトやると女にモテるよ!」
という先輩の勧誘の言葉にまんまと引っかかったからです。
私は3年間続けていたソフトテニスをあっさり辞めてアメフト部に入部しました。
(「モテるよ!」は清水国際アメフト部の伝統的な勧誘文句です。)
そんな不純な動機ではじめたアメフトですが、私の将来を大きく変化させる出会いが待っていました。
恩師である上松監督に出会ったのです。
この出会いが私の人生を変えたといってもいいと思います。

話を戻します。
女子にモテると誘われ入部し、初めてアメフトの試合を見た時は度肝を抜かれました・・。
タックルを受けた先輩が紙のように吹っ飛ぶ姿を見て、とんでもない部活に入ってしまったと思ったものです。
そして、お返しとばかりにタックルをして、相手を倒した先輩がガッツポーズをしていました。
ケンカと変わんないじゃん・・・。
アメフトは今までの私のスポーツの概念とは全く違ってました。
集団で行なう格闘技のようなものです。
実際にその通りで、戦争をスポーツにした陣取り合戦ゲームだったのです。
事実、ラグビーと比較した場合、
アメフトのケガの発生率は約3倍です。
アメフト9.51
ラグビー2.78
(某損保会社の統計より)
その時、安易な気持ちで入部したことに後悔しました・・・。
やると決めた以上、いつかは試合に出なければならない。
でも、このままでは殺されてしまう・・。
大げさだと思われるかもしれませんが、本気でそう思ったのです。
先輩達は明らかに私と体格が違う。
そんな恐怖から、先輩やコ監督の指導のもと、基礎トレーニングをみっちり行いました。
いや、やらされました。
この基礎トレーニングが最初は本当に苦しいのですが、だんだんと慣れてきます。
そのうちに身体が大きくなり、はじめての試合に参加しました。
はじめてのアメフトの試合は、
痛い!より、クサイっ!!
高校のアメフトでは、1年生は試合にでることが少ないです。
基礎体力づくり、身体づくりを意図してみっちりとトレーニングを行います。
タックルは受けてみるとかなりの衝撃があるのですが、準備をしていれば滅多なことではケガはしません。
私も公式戦で最初のタックルを受けた時はそう思いました。
事実、私は大きなケガを一度もしたことがありません。
それより押しつぶされ時の相手選手の汗、体臭、土の匂い・・・。
使い込んだ防具に染み付いた強烈な刺激臭が鼻をつきました。
とても臭かったです・・・。
頭の中の想像と自分でやってみるとは大違いです。
その後、私は上松監督の指導のもと、2年生でライン(ぶつかることが仕事の前衛のポジション)
をはじめ、全てのポジションを経験しました。
監督の考えはわかりませんでしたが、当時も今も清水国際高校アメフト部は人数が少なく、ポジションの兼任が普通でした。
結局、クォーターバック(ボールを投げたりする司令塔)のポジションに落ち着きました。
3年生でキャプテンに就任し、清水国際初の県大会春秋連覇を達成。
本当に貴重な経験、体験をさせていただきました。

関東学院大学へ進学後も、アメフトを続けました。
その時にポジションがワイドレシーバー(ボールをキャッチするポジション)に変わりました。
他のチームメイトと比べて、ポジションチェンジがスムーズにできたことで、上松流のトレーニングの効果を実感しました。
上松監督のトレーニングは選手を早く実戦に投入することを目的にした無駄のないトレーニングでした。
そんなアメフト漬けの大学生活でしたが、成人式に出席した時、ある気付きを得ました。
中学の同級生たちと再会した時に
「早川大きくなったよね」
「お前ゴツいね・・・」
と言われたのです。
何気ない会話に思われるかもしれませんが、この時まで
自分のことを客観的に見て振り返る機会がありませんでした。
なぜなら、高校から大学在学時まで目まぐるしく忙しい毎日だったからです。
私は、大学のアメフト選手の中では平均より細身な体格です。
決して大きな方ではありません。
中には190cm以上で120キロを超える怪物のような体格の選手もいるのです。
そんな選手が自分を倒す?ために本気で追いかけてきます。
あらためて考えると恐ろしい世界です。
そんな選手と自分を比べると、オレは小さいなあ・・。
と日頃から思っていたのです。
しかし、同級生は私のことを大きい、ゴツいといいます。
考えてみれば、中学卒業時の
私の体型は身長170cm。
体重は53kgでした。
ガリッガリのもやし体型です。
当時の私は、身長173cm。
体重は70kgくらいはあったと思います。
私の身体はアメフトなしで大きくなったわけではありません。
アメフト部に入らなければヒョロヒョロ体型のままだったと思います。
人間の体は、環境に適した体に成長していくのだと気が付きました。
いくら栄養をとっても、運動をしなければ体が成長することはありません。
プロティンをいくら飲んでも、運動をしなければ筋肉は付きません。
これは紛れもない事実です。
アメフト部のトレーニングをしているうちに、私の身体はいつの間にか同級生より
大きな身体になっていました。
しかも、動きやすく怪我のしにくい身体です。
そんな体験もあり、身体のメカニズムなどに興味を持ち、トレーニング関係の専門学校に入学し、様々なトレーニング理論を学び卒業しました。
卒業と同時に実家を改装してジムをオープンしました。
また上松監督の誘いもあり、母校の清水国際高校アメフト部のヘッドコーチに就任。
後輩のスキルやトレーニングなどを指導するようになりました。
この母校での後輩を指導する体験は私にとって更に貴重な経験になりました。
最初に戸惑ったのは、トレーニングを受ける選手の立場と教える指導者の立場は、全く違うということです。
選手の気持ちを察し、モチベーションをコントロールしながらポテンシャルを発揮する為のトレーニングを行ってもらわなければいけません。
しかもアメフトは高校から始めるスポーツです。
当たり前ですが、1年生は全員がヒヨコにも満たない卵の存在です。
選手の時には考えもしなかった様々な困難に直面しました。
また、他のスポーツに比べるとアメフトのポジションは専門職という傾向が強いです。
ボールを蹴る専門の選手。
パスをする専門の選手。
キャッチする専門の選手。
走って敵の守りを突破する選手。
自陣への敵の侵入を食い止める選手がいます。
それぞれのポジションに必要となる特化した技術があり、その分野を伸ばす練習と基礎能力を伸ばすトレーニングが必要になります。
さらに個々の特性だけではなく、チームの作戦、特色とも融合していかなければなりません。
上松監督流の指導方法
トレーニングメニューの作成の方法
を実戦で学ばせて頂き、徐々に自分なりにアレンジを加えさせてもらいました。
選手のポジション、体質、性格を考えてトレーニングを考え、能力が向上したか判断し、またトレーニングを考える。
試行錯誤でテストし続けました。
最初は思ったように成果が出なかったのですが、少しずつ、自分の納得の行く成果が出せるようになってきました。
トレーニングを教えるうえで
大事なことは認めること。信じること。
そして自分を信じることです。
入部当初の一年生は、様々な劣等感を抱えています。
中には自分を信じれない生徒もいます。
私もそうでした。
まわりと自分を比べて落ち込んだこともあります。
そんな中、上松監督やコーチ、先輩に褒められ認められて何とかやってきました。
そういった生徒がまず見るのは指導者の姿勢です。
この監督、コーチの人は自分たちにいうことを自分も実践しているのか?
ということです。
我々指導者自身が自分を信じ、行動することで、その姿勢が段々伝わっていきます。
その姿勢が選手に伝染し、選手自身も少しづつ自分を信じるようになっていくのです。
そんなことを上松監督から教えてもらいました。本当に貴重な経験でした。
その経験が、今のトレーニングの考えの土台にあります。
こんなことを書くとスポーツの分野に特化したトレーナーと思われそうですが、
ボディメイクやダイエット。
病気入院後に歩くためのトレーニング。
選手のポテンシャルUPのトレーニングまで幅広く行ってます。
アメフトのポジションごとの選手のトレーニングの経験が活かされてます。
体重を増やすトレーニングに比べれば、余分な脂肪を落とすトレーニングは意外と簡単です。
様々な案件の依頼をこなすうちに私が学んだトレーニング理論はダイエット、リハビリなどに応用可能なことが分かりました。
クライアントの要望に合わせて、体作りを無理なくリスクの少ない方法でサポートしてます。
しかし、私は治療家ではないので、あくまでご自身の身体を自分の力で何とかしたいという意志が必要になります。
最近は見た目の筋肉を大きくするトレーニングが好まれる傾向にありますが、必要な動作がスムーズにできることも重要です。私のところにくる方のほとんどが体のバランスが悪くなっています。
そのバランスをある程度、元に戻すことからトレーニングをはじめています。
ウォーミングアップせずに、いきなり高負荷のダンベルなどでトレーニングをする方もおられます。
人間の関節は消耗品です。
高負荷によって、関節にダメージを与えてしまうと、年齢を重ねたあとに悩まされることになるのです。
そうなっては本末転倒です。
段階を追って、徐々に負荷を高めたトレーニングを設計します。
あなたがいつの間にか目標を達成する。
それが私の理想の指導方法です。
まずは気軽に電話でご相談ください。
あなたの体のことを一緒に考え、目標を一緒に達成するのが、私にとって大きな喜びです。
